「反日メディアの正体」感想
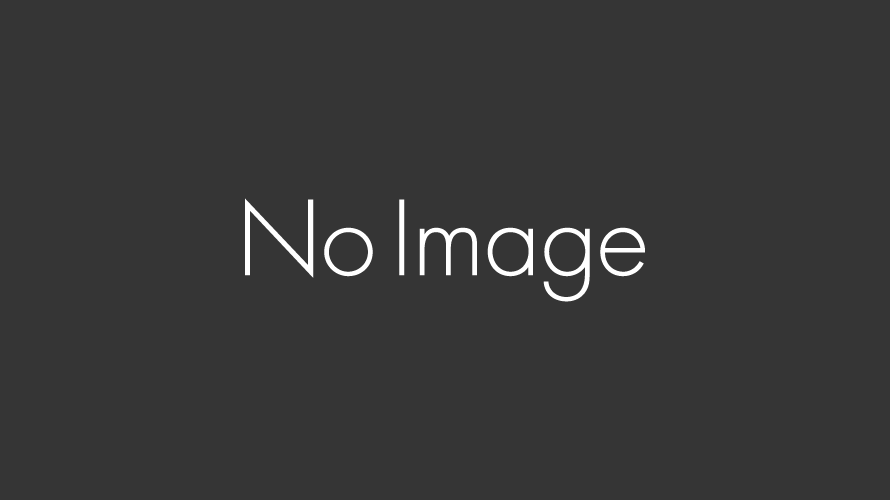
チャンネル桜の「さくらじ」やチャンネルグランドストラテジーの「全力古谷 サブカルから見る日本」でおなじみの古谷経衡さん。彼の著作を読むのは「ネット右翼の逆襲」に続き2作目。
「ネット右翼の逆襲」も単なる著者の主張ではなく、アンケートに基づく冷静な筆致が特徴でしたが、この「反日メディアの正体」はなおさら彼の客観的な視点がうかがえる。
メディアに在日外国人が入り込んでいる、というのはありふれた言説だ。実際にそれは間違いではないのだろう。しかし、著者はそれだけが原因ではないという。問題はメディアの国民との皮膚感覚からの遊離、メディアの「閉鎖性」「特権意識」「安定」がそろったときの危険性にある、それと同じような状態の説明にあさま山荘事件にかかわったテロリストや学校教員の例を挙げた説明は非常にわかりやすく興味深かった。それだけではなく、メディアが「社会の公器」から敗戦責任を政府になすりつけ、それを知りつつ国民が受け入れてきた構図、それが現在崩れかけているのが現代なのだろう。
興味深かったのは、著者のネットに対する態度だ。先ほどから何度も繰り返しているが冷静で客観的なのだ。それこそ、著者はインターネットという媒体を通じて世に出てきた人だと思うのだが、ネットの力を過信せず、あくまでインターネットは、テレビの反射空間だと指摘する。その上で最近になって増えてきたインターネットユーザーの閉鎖性も指摘している。確かに、最近私はTwitterを始めたのだが、まず、自分がフォローする人を選ぶ。そのうえでツイートとしたりリツイートしたりすることを繰り返していくうちに、自分をフォローしている人が出てくる。ただ、意識してフォロワーを選ばないと、自分と似たりよったりの考えの人ばかりになり、入ってくる情報も限定的なものになってしまう。私のように自分の意見や情報を拡散するためにやっているものですらそうなのだから、友人と情報を共有するためだけにやっている人ならなおさらだろう。結局新しい媒体を手に入れても、そこで閉鎖空間を作ってしまっては、閉鎖性ゆえに歪んでしまったマスメディアとなんら変わることがなくなってしまうだろう。
全体の感想としては、さまざまなデータや歴史的な検証によって書かれた本書は大変読みやすく、新たな視点に気付かされた。「ネット右翼の逆襲」も面白かったが、こちらのほうが内容的には堅いもののするすると読める感じでした。
しかし、前々回の記事でも取り上げましたが、フジテレビの新年の看板を見た限りでは、マスメディアと国民の感覚のかい離は広がるばかりのような気がします・・・。
※こちらの記事は平成26年1月9日に書かれたものです。
-
前の記事
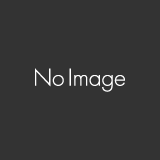
「ジャパニズム」16号感想 2019.02.24
-
次の記事
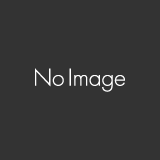
倉山満 「嘘だらけの日韓近現代史」感想 2019.02.25
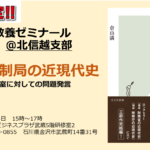
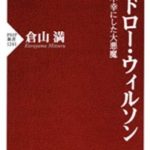

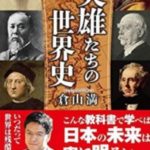
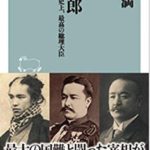
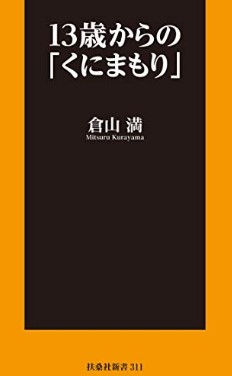
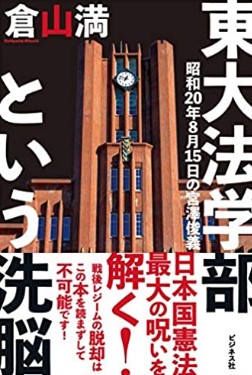

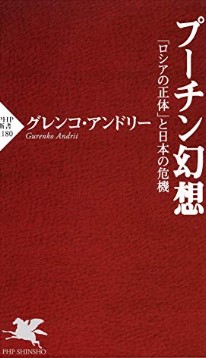
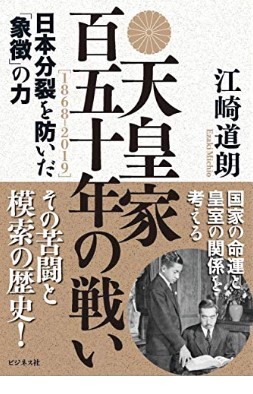
コメントを書く