江崎道朗 『 コミンテルンの謀略と日本の敗戦 』 感想
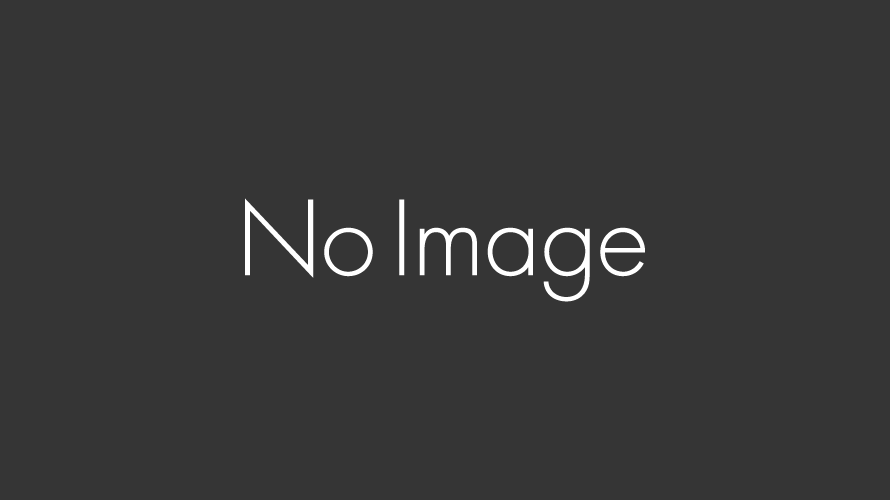
祝!!江崎道朗先生、第一回アパ日本再興大賞受賞!!(ノ゚ー゚)ノ☆パチパチ☆ヾ(゚ー゚ヾ)
公益財団法人アパ日本再興財団主催 第一回アパ日本再興大賞受賞者発表 江崎道朗氏の「日本は誰と戦ったのか コミンテルンの秘密工作を追及するアメリカ」が受賞!
というわけで?遅ればせながら、1年以上前に発売された著作ですが、『コミンテルンの謀略と日本の敗戦』の感想です。いろいろ読んで書き留めてはなかなか書けない悪循環に。。ゴニョゴニョ。えーと気を取り直して。
こちらは涙を流しながら読む本です。涙にはいろんな涙があります。悲しさや切なさ故に溢れ出す涙。感動とともに流す温かな涙。登場人物の理不尽な境遇に共感しながら流す怒りの涙。この本を読んだ時と同じような感覚になったのは堀栄三の『大本営参謀の情報戦記』や倉山満先生の『帝国憲法物語』でしょうか(どちらも感想を書いていますので、宜しければお読みください_(._.)_ 堀栄三 大本営参謀の情報戦記 感想、倉山満 「帝国憲法物語」感想)。
前著は情報を軽視し、そして本当に大切な情報を握りつぶすようなことをした人がいたために、日本がいかに愚かな戦いをしたのかを思い知らされました。先の大戦の評価は様々です。ある人は「アジア解放のための聖戦だ」と言います。ある人は「勝てるはずのないアメリカと戦った日本はすごい国だったのだ」と。私は国のため、残された人のために戦って死んだ人は本当に偉かったと思いますし、感謝しています。しかしながら、戦死よりも餓死が多いという作戦も何もないやり方をしたこと。このような戦争をしてしまった人への怒りや反省もないままにこの戦いを美化すべきでは無いと思います。
そして、『帝国憲法物語』。日本を列強に飲み込まれない強い国にするために奮闘した先人達。その思いの結晶が「大日本帝国憲法」でした。しかし我々は敗戦でその憲法を奪われてしまいました。このことへの反省や痛み無くして改憲論議をして何の意味があるのでしょうか。憲法に「自衛隊」を書き込んだら、戦地に充分な物資は送られるのでしょうか。自衛隊に予算をつけるなど憲法改正をせずとも出来るはずです。自衛隊に名誉を与えることも。なぜそれをせずに改憲なのでしょうか。
本書はコミンテルンや彼らの歴史についても語られています。しかしながら日本が彼らの謀略に嵌められたからあの戦争をし、負けたという話ではありません。実際に起こったことは「日本の自滅」でした。ならば昔の日本人は愚かだったのでしょうか?
日本は昔から識字率も高く、民間での教育も盛んでした。明治維新は薩長の志士たちを中心として行われましたが、薩摩藩は「郷中教育」といって地域の子供たちが互いに学問や武道、道徳も教え合う習慣があり、西郷隆盛と大久保利通も、そんな中で幼い頃から研鑽した仲間でした。長州の志士たちも「適塾」や「松下村塾」で日本の将来を我が事と考え学んで来た人達が中心でした。その彼らが築き上げた明治以降の日本はどこからおかしくなったのでしょうか。
江崎先生は、日本が列強に飲み込まれないように必死に学ぶエリートたちは、その使命感故に、西洋を学ぶことを、日本の伝統を否定することと誤解してしまった、そこから「エリートの日本」と「庶民の日本」が分断されてしまうという悲劇が起こったといいます。そして当時の日本はイギリスよりも多くをフランスやドイツから学んでおり、流行していた政治思想が、「進歩主義」と「社会主義」だったと。
富国強兵を目指し、近代産業国家へと突き進んでいけば、当然、労働問題や貧困問題に行き当たります。それを解決するために社会主義に傾倒していくのは仕方のない側面もあります。しかもその過程で日本は、特に大正から昭和にかけて経済政策に失敗します。
そして、私も常々思うのですが、なぜかいわゆる保守と呼ばれる人たちは、社会保障政策に対して疎いし冷たい。明治23年の第一回帝国議会で、第一号法律案として「窮民救助法案」が提出されました。しかしながら「なぜ一部の困窮者を助けるために国民の税金を使うのか」との批判が多数を占め、衆議院はこの法案を否決してしまいました。このような状態では心ある若者がますます社会主義に傾倒してしまうことも頷けてしまいます。
このような状況で「エリート」は大正時代以降、主に三つのグループに細分化していたと江崎先生は語ります。
第一が社会主義にのめり込んだ「左翼全体主義」のグループで、彼らはソ連・コミンテルンの「秘密工作」に呼応していく。
第二は、資本主義と議会制民主主義を批判し、内心では社会主義に共感しながらも「左翼」を弾圧した「右翼全体主義者」。
第三は、聖徳太子以来の政治的伝統を独学で学び、不完全であっても資本主義、議会制民主主義を尊重し、統制経済に反対し、コミンテルンに警戒心を抱き、皇室のもとで秩序ある自由を守ろうとした「保守自由主義者」。
このような中で政府や「右翼全体主義者」のやり方は愚かでした。彼らは社会主義に理論的に反論するのではなく、ただ取り締まりと弾圧で臨みました。結局彼らのやったことは、困窮者を思い、それを解決するために社会主義を学んでいた人達を反体制側に追いやることになってしまいます。
共産主義の脅威が高まると、政府は治安維持法(大正14年)で活動家を取り締まり、共産党は機能しなくなりましたが、そのことにより偽装転向者が軍の中枢部や革新的官僚の中に入り込むこととなりました。なぜ彼らが簡単に入り込めたのか?それは結局は「右翼全体主義者」が行った弾圧にあります。共産主義や社会主義を学ぶだけで非難されるような言論空間になれば、当然、敵のことを知るためにそれを学ぶということも困難になります。それでは結局、敵の手口を知ることも出来ず、術中にはまってしまっても当然です。その結果どうなったのでしょうか。
社会主義を批判しているにも関わらず、「右翼全体主義者」達は彼らの術中にはまったかのように統制経済を進め、憲法が制定されたときは、立憲君主国を目指していたはずなのに、美濃部達吉の「天皇機関説」は徹底的に批判され、弾圧されました。天皇親政を叫んで起こされた二・二・六事件ですが、あの精神的支柱とされた北一輝の『日本改造法案大綱』といい、現代の我々から見たら共産主義革命と何が違うのかさっぱりわからないものです。
そしてさらに悲惨なのが、政府や「右翼全体主義者」たちが、「左翼全体主義者」のみならず「保守自由主義者」をも弾圧したことです。東条英機に関してはあの理不尽な東京裁判のせいで処刑された彼に同情する人も多い。しかしながら、彼が開戦したにも関わらず、どのように終戦に持ち込むかのプランもなく、それに関して発言した人達を弾圧し、拘束し、そして死地に配置転換したことも事実なのです。
本書を読むことでなぜそのような状況になってしまったのかを垣間見ることができます。しかしながら、江崎先生は言います。この本は過去を反省するためや、一部の人達を断罪するためのものではなく、賢く、強い日本を築いていくためのものだと。
私は、以前に2冊の江崎先生の本の感想を書きました。
このブログでメインで取り上げている倉山満先生の著作にも通ずることですが、単なる歴史や評論のための本ではありません。その事象が「どうだったか」、あるいはそれを検証して「どうなるか」を予測するのではなく「どうするか」を考えるための本なのです。
この本で大変興味深かったのが、「保守自由主義者」とされた人達。小田村寅二郎を中心とする学生グループの「日本学生協会」とその卒業生たちによる民間シンクタンクの「精神科学研究所」の関係者たちです。なぜ彼らがこのような言論状況にあっても日本が陥りつつあった危機を的確に見て取ることが出来たのかです。それは彼らが積み重ねてきた思想的鍛錬にあると江崎先生は言います。改めて学ぶことの大切さについて感じます。
現在の我々はこの戦前の言論状況を「愚かだった」と一笑に付すことが出来るのでしょうか。それどころか、所謂「保守」と呼ばれる愛国者たちが、まるであの戦争を「聖戦」であったかのように語ることに戦慄を感じます。そして、なぜか多くの保守と言われる人が、自由主義経済を「新自由主義」などとレッテル貼りし、民間を軽視し、「規制緩和」との言葉を発しただけで発狂して、大きな政府と統制経済を叫ぶのです。保守というのは定義するのが難しい概念です。もともとは定義する必要がなく、「革新」に対するものとして生まれたものだからでしょう。いつから日本人は「大きな政府」や「統制経済」を「保守」だと勘違いしてしまったのでしょうか。日本の歴史は戦前のほんの70数年前からの一時代ではないはずなのに。
「コミンテルン」に関する研究や本も未だに少ない我が国の状況。「保守自由主義者」小田村寅二郎に関しても、初めて知るかたも多いのではないでしょうか。これからの国の行く末を考えるための必読の書です。読み始めたら止まらなくなること間違いなし!お薦めです!!
※こちらの記事は平成30年11月11日に書かれたものです。
-
前の記事
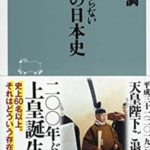
倉山満 国民が知らない上皇の日本史 感想②三種の神器とは 2019.03.17
-
次の記事
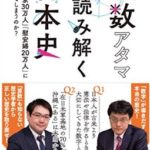
倉山満 平井基之 理数アタマで読み解く日本史 ─なぜ「南京30万人」「慰安婦20万人」に騙されてしまうのか? 感想 2019.03.17
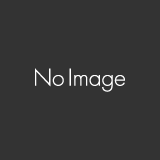
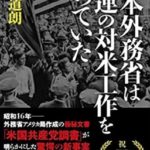
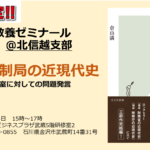
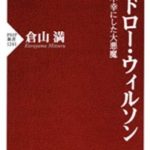

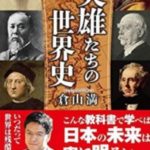
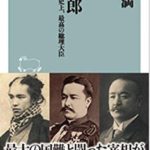
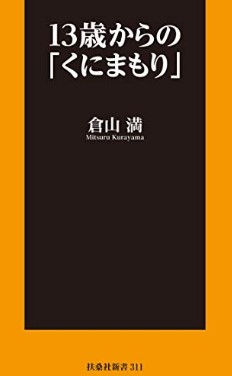
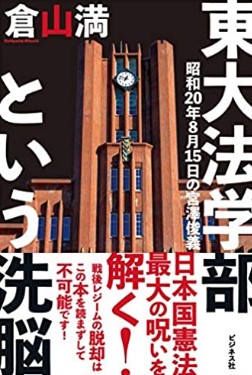

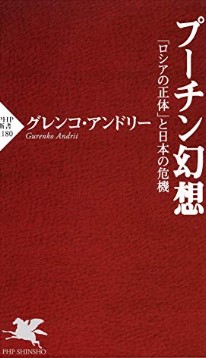
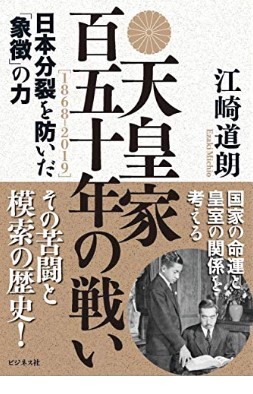
コメントを書く