江崎道朗 『アメリカ側から見た東京裁判史観の虚妄』 感想
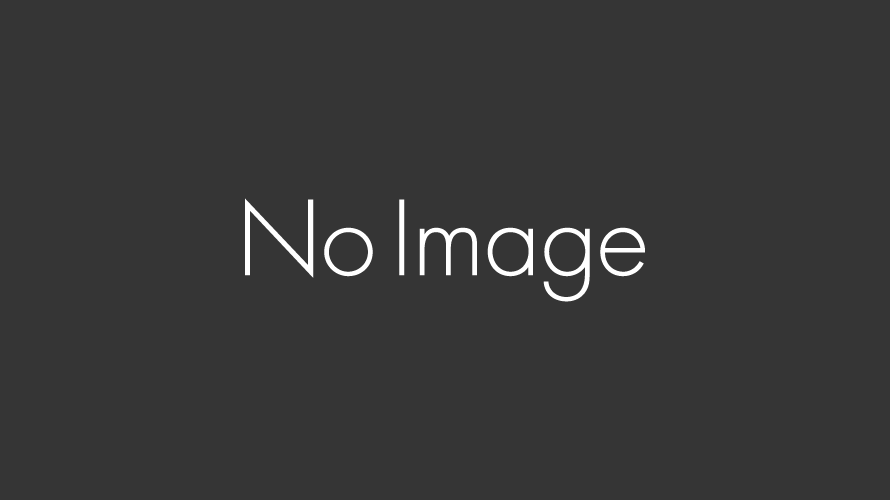
「ヴェノナ文書」
これについて聞いたことのある人は多いだろう。しかし「ヴェノナ文書」とは一体どのようなものなのか。本書の中ではこのように説明される。
P67より引用
ヴェノナ文書とは、ソ連・コミンテルンのスパイたちの更新記録だ。
正確に言うと、一九四〇年から一九四四年にかけて、アメリカにいるソ連のスパイとソ連本国との暗号電文をアメリカ陸軍が密かに傍受し、一九四三から一九八〇年までの長期にわたって、アメリカ国家保障局(NSA)がイギリス情報部と連携して開設した「ヴェノナ作戦」に関わる文書のことである。
引用終わり
F・ルーズベルト政権内にも当時のアメリカのマスコミ内部にも多くのソ連のスパイが入り込んでいた。そして彼らは日本とアメリカを戦争へと追い込むための工作を仕掛け、戦後はGHQの一員として、日本の占領政策や現行憲法制定にも関与していのだ。
現在、アメリカでは、特に保守派の間では近現代史の見直しが起こっているという。しかしながらそれは民間レベルの話で、アカデミズミの世界ではやはり日本同様、左派の影響が強いという。
日本の歴史学会では「コミンテルン」の名前を出しただけで、実証主義ではないとまともに取り上げられないそうだ。しかし、コミンテルンは陰謀論ではない。
この「ヴェノナ文書」は1995年にアメリカ政府が情報公開法に基づいて公開したものだ。日本の歴史学者はなぜこれを無視するのか。少なくとも日本の大手の教科書にはこれを検証し、取り入れた形跡は見られない。
日本国憲法の制定に関わったビッソンはソ連のスパイだった。元々は英語で書かれていたGHQの作った憲法草案を翻訳する過程で、白洲次郎たちはなんとか日本の国体を守るために、日本側に都合のいいようにしようとしたが、それはビッソンたちによって阻まれている。
皇室の条項について、「すべての皇室財産は、世襲の遺産を除き、国に属する」と邦訳しようとしていたのに、「世襲の遺産を除き」という言葉が彼らによって削除させられたのだ。現在、皇室財政が逼迫し十一宮家が臣籍降下せざるを得なくなったこともここからつながっている。しかしながらそのようなことは我々は学校では教わらない。帝国憲法下では天皇主権で、人権は法律によって制限され、自由な言論や政治活動は制限されていた。日本国憲法によって、戦前の天皇主権が否定され、国民主権となり人権の保障が著しく強化されたと一方的に歪められた形で教わるのだ。
本書で江崎先生は「二十世紀は、ソ連・コミンテルンとの戦争であった」という「百年冷戦史観」を提唱している。この百年冷戦史観の観点から、日米の保守派は、東京裁判史観の見直しで共闘すべきだと。
ソ連の崩壊で冷戦は終わったと思う人も多いかもしれない。しかし、ソ連が崩壊したからと言って、コミンテルンの末裔たちが絶滅したわけではない。日本でも、前回の衆議院選挙では共産党は議席を伸ばし、現在、根本的な主張が違うはずの民進党などの野党を取り込もうとしている。以前、「国民連合政府」の構想を共産党が打ち立てたのは「安保関連法制(彼ら曰く戦争法案)廃止と安倍政権打倒」を目的としての共闘しようというものだった。このように「平和」や「戦争反対」などの名目で、彼らの主張に共感する者たちを、巧みに取り込み、自分たちの利益のために働かせる。ここが彼らの恐ろしいところだ。
今回つくづく感じたのが、共産主義者の恐るべき執念深さと保守派のナイーブさだ。
昨今の若者中心で結成された(とされていた)SEALDsとて、決してうまくいっていたとは思わない。しかし、解散したはずの彼らが、最近では沖縄や原発反対運動で活動しているように、失敗してもまた形を変え、目的達成のために何十年もかけて工作活動を続けるのだ。
そして、彼らは手段を選ばない。
本来の彼らの主張からすれば、共産主義と宗教は相いれないはずだが、彼らは目的のためなら宗教団体にも潜入して活動する。こちらの是非はともかくとして、とかく保守派は正しいことを主張していれば、いずれ自分たちが認められると思っているようにしか見えない。マスコミが左翼で席巻されていることを批判するのは良いが、批判するだけではなく、どうすれば自分たちの主張が取り上げられるようになるのか。自分たちがそこで主流派になれるのかを真剣に考えるべきではないだろうか。
「ヴェノナ文書」が公開されたことによって、少しずつ解明されていることはあるとはいえ、未だに謎の部分は多い。アメリカ側はもちろん、日本の外務省も当時アメリカでの反日活動の背後にアメリカ共産党・コミンテルンの暗躍があることを正確に分析し、日米分離工作にのらないように近衛内閣に訴えていた。しかしその声に近衛内閣は耳を傾けず、親ソ反米政策を推進し、ルーズベルト政権も対日圧迫外交を強化していった。近衛の近くで尾崎秀実などのスパイが暗躍していたことは知られているがそれは氷山の一角だろう。「ヴェノナ文書」の中にはモスクワと東京の交信記録もあるそうだ。アメリカ側からだけではない、日本側からの研究も待たれる。
残念なことに、日本で中西輝政氏の翻訳した「ヴェノナ」は絶版になっており、古本でも手に届かないような値段となっている。なんとか再販か電子書籍化してもらえないかと思い、kindle化のリクエストもしているのだが、現在ではその予定はないらしい。これだけ高額で古本が取引されるほど需要があるにも関わらず、なぜ再版されないのか。出版業界にも大きな闇があるのか。どちらにしても正しく歴史を検証しようという声が、無視できないほど大きくなるよう、保守派は左派に負けることなく作戦を立て、執念深く活動を続けなければならない。
※こちらの記事は平成28年10月10日に書かれていたものです。
-
前の記事
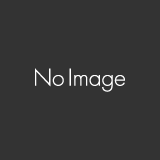
倉山満 『大間違いのアメリカ合衆国』感想 2019.03.11
-
次の記事
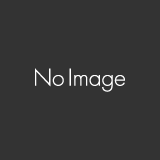
江崎道朗 『マスコミが報じないトランプ台頭の秘密』感想 2019.03.12
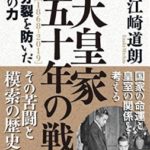
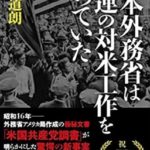
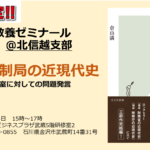
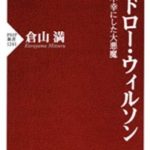

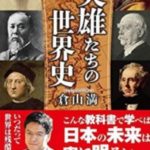
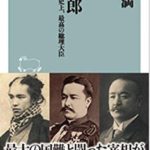
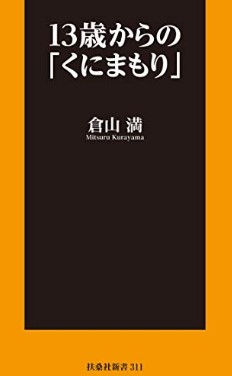
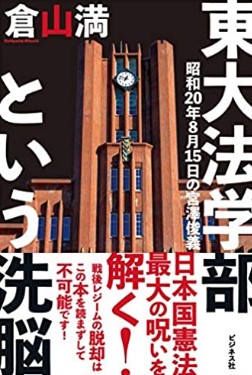

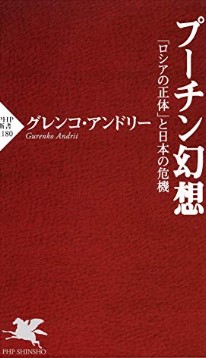
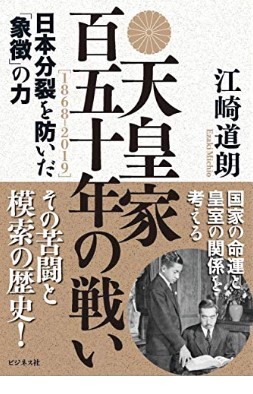
コメントを書く