倉山満「帝国憲法の真実」 感想
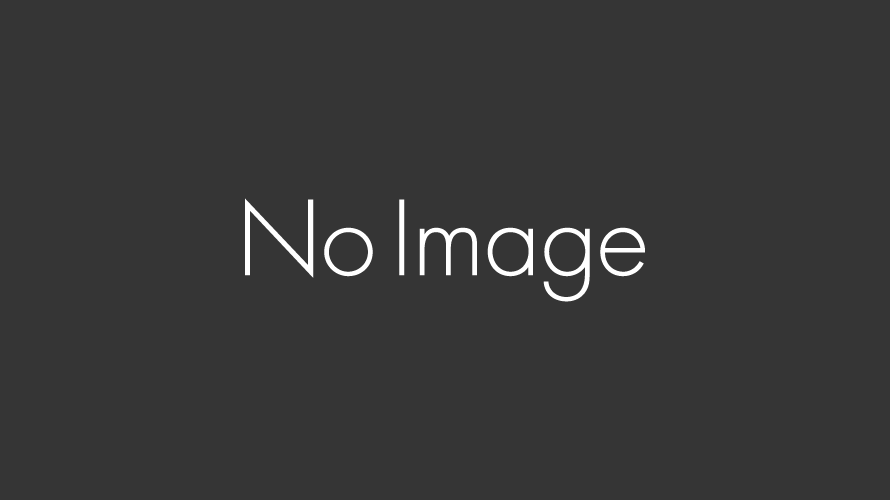
「帝国憲法」に正面から向き合う、倉山満先生の新作。
本当は「日本国憲法の暗号と帝国憲法の真実」というタイトルにする予定だったのが、日本国憲法があまりにもグダグダなので、タイトルから外したとか。
第一部で日本国憲法の欺瞞について、第二部で帝国憲法の真実について書かれていますが、私が最も感銘を受けたのは、第二部第三章の「自由の根源に迫る」です。
日本国憲法では、第十九条で良心の自由、第二十条で、信教の自由が掲げられています。帝国憲法では第二十八条に信教の自由に関する条文がありますが、「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」との制限があります。とすれば、日本国憲法下にある現代の日本は自由の保障された素晴らしい社会なのでしょうか。
まず良心の自由ですが、これは本来制限しようがなく裁判の対象になりえません。その人が内心で何を思っているかなど知りえないことだからです。それをやってしまったら中世の魔女狩りと変わらないことになります。では日本国憲法下では良心の自由が守られているのでしょうか。マッカーサーは、日本国憲法を押し付けておきながら、レッドパージをしています。裁判所は、良心の自由の侵害を訴えた人たちの請求を棄却しています。マッカーサーは日本国憲法より上、ということです。倉山先生は、憲法や法律は条文ではなく運用が大事だということをいつも言っているのですが、どんなに立派な条文があってもそれが守られなくては何の意味もないですね。
信教の自由はどうでしょうか。今の日本ではオウム真理教がアレフと名を変えて存在することを許していることを思えば確かに守られているのでしょう。しかし、無制限に自由を認めることが本当に良いことなのでしょうか。この章ではかなり、いろいろな宗教問題に切り込んでいますが、憲法を学ぶ人ならだれでも知っている「エホバの証人輸血拒否」の事例もあげています。信仰の問題が絡むと、何が正しいのかを判断することは容易ではありません。ただ成人した信者が自分の意志で輸血を拒むのならまだしも、緊急手術の必要な子供の場合はどうするのか。信仰と人の命の重さ、それを法でどのように運用するか。答えを出すのはあまりに重い問題ですが、実際に起こりうることに目を背けるわけにはいかないでしょう。さらなる議論が必要だと思われます。
以前「誰が殺した?日本国憲法」の感想をUPし、そちらは集団的自衛権の観点から感想をあげていたのですが、この本でも、良心の自由及びさまざまな人権についての考察がなされています。日本国憲法は様々な人権を保障し、なおかつ憲法十三条から無数に権利が増殖できる仕組みになっていますが、先ほども述べたとおり、どんなに条文でそれを保障していても、それが正しく運用されなければ意味がありません。
今回の「帝国憲法の真実」他、何冊もの憲法に関する倉山先生の著書において、条文だけ立派なのに結局それが守られない現在の日本国憲法運用に関する怒り、その怒りの中に先生の人としての優しさが読み取れます。そして、なぜ倉山先生がときに過激なまでに意見の異なる人のことを攻撃(口撃)するのかが、こちらの本を読んでわかった気がします。「保守の心得」に続く「保守入門シリーズ」。第三作が出るのはまだ先になりそうですが、本当に楽しみです。
※こちらの記事は平成26年5月10日に書かれたものです。
-
前の記事
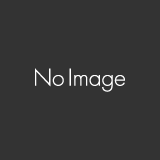
倉山満 「増税と政局・暗闘50年史」感想 2019.03.02
-
次の記事
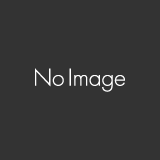
ケーススタディー 三橋貴明「真冬の向日葵」を検証して名誉毀損について考える 2019.03.02
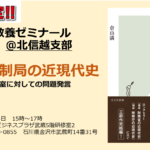
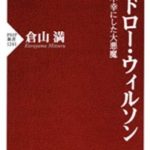

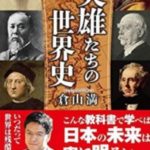
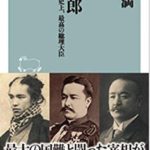
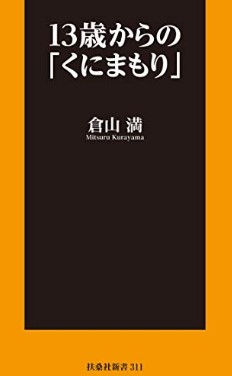
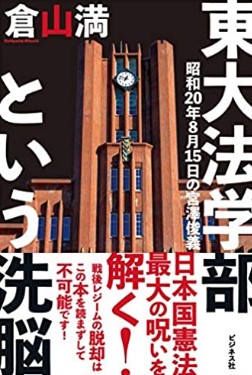

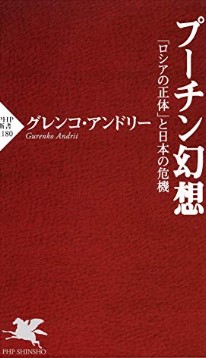
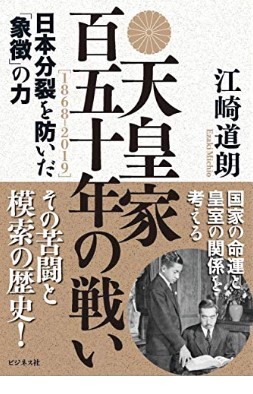
コメントを書く